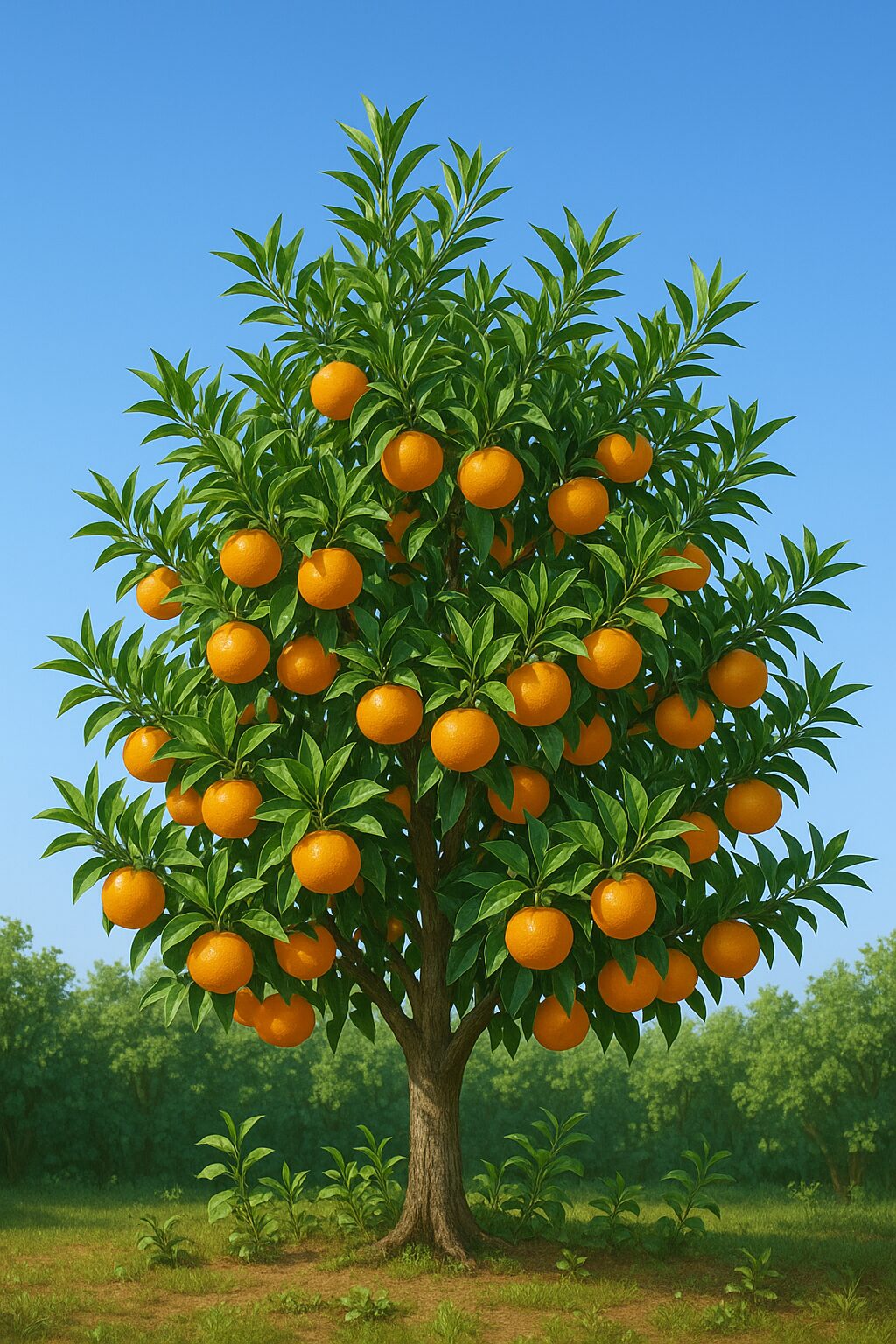 大切に育てているみかんの木に実がならないと、がっかりしてしまいますよね。「今年こそは」と期待していたのに花が咲かない、実がなるまで何年待てば良いのだろう、といった悩みは、家庭でみかんを育てる多くの方が抱える共通の疑問です。また、そもそも庭に植えてはいけないという話を聞いて不安に思う方もいるかもしれません。
大切に育てているみかんの木に実がならないと、がっかりしてしまいますよね。「今年こそは」と期待していたのに花が咲かない、実がなるまで何年待てば良いのだろう、といった悩みは、家庭でみかんを育てる多くの方が抱える共通の疑問です。また、そもそも庭に植えてはいけないという話を聞いて不安に思う方もいるかもしれません。
みかんの木に実をつけるには、木の寿命や、実が落ちる原因を理解することが欠かせません。適切な時期の剪定や、効果的な肥料の与え方、そして花が咲いたら行うべき手入れなど、いくつかの重要なポイントがあります。これらの知識不足が、失敗や後悔につながることも少なくありません。
この記事では、みかんの木に実がならないさまざまな原因を徹底的に掘り下げ、誰でも実践できる具体的な解決策を分かりやすく解説します。
ポイント
-
みかんの木に実がならない根本的な原因
-
樹齢や生育環境が収穫に与える影響
-
実を安定してつけさせるための具体的な手入れ方法
-
みかん栽培でよくある疑問や俗説の真相
みかんの木に実がならない主な原因
-
そもそも花が咲かないのはなぜ?
-
みかんの実が落ちる原因は生理現象かも
-
みかんの木に実がなるまで何年かかる?
-
みかんの木の寿命と収穫量のピーク
-
庭に植えてはいけないという俗説は本当?
そもそも花が咲かないのはなぜ?

みかんの木に実がつく大前提として、まず花が咲く必要があります。花が咲かない場合、いくつかの原因が考えられます。
最も多い原因は、日照不足です。みかんは日光を非常に好む植物で、光合成を活発に行うことで花芽を形成するエネルギーを蓄えます。植え付け場所の日当たりが悪い、または成長した他の木や建物の影になっている場合は、十分な光を得られず花が咲きにくくなります。
次に、肥料の過不足も花つきに影響します。特に、窒素成分の多い肥料を与えすぎると、葉や枝ばかりが茂る「枝葉過繁茂(しようかはんも)」という状態になり、花芽の形成が抑制されることがあります。逆に、花芽を作るために必要なリン酸やカリウムといった栄養素が不足していても、花は咲きません。
また、剪定の時期や方法の誤りも大きな原因となります。みかんの花芽は、前年に伸びた春枝の先端付近につくことが多いです。そのため、春以降に強く剪定してしまうと、せっかくできた花芽を切り落としてしまうことになります。剪定は、花芽が動き出す前の2月から3月上旬に行うのが基本です。
みかんの実が落ちる原因は生理現象かも
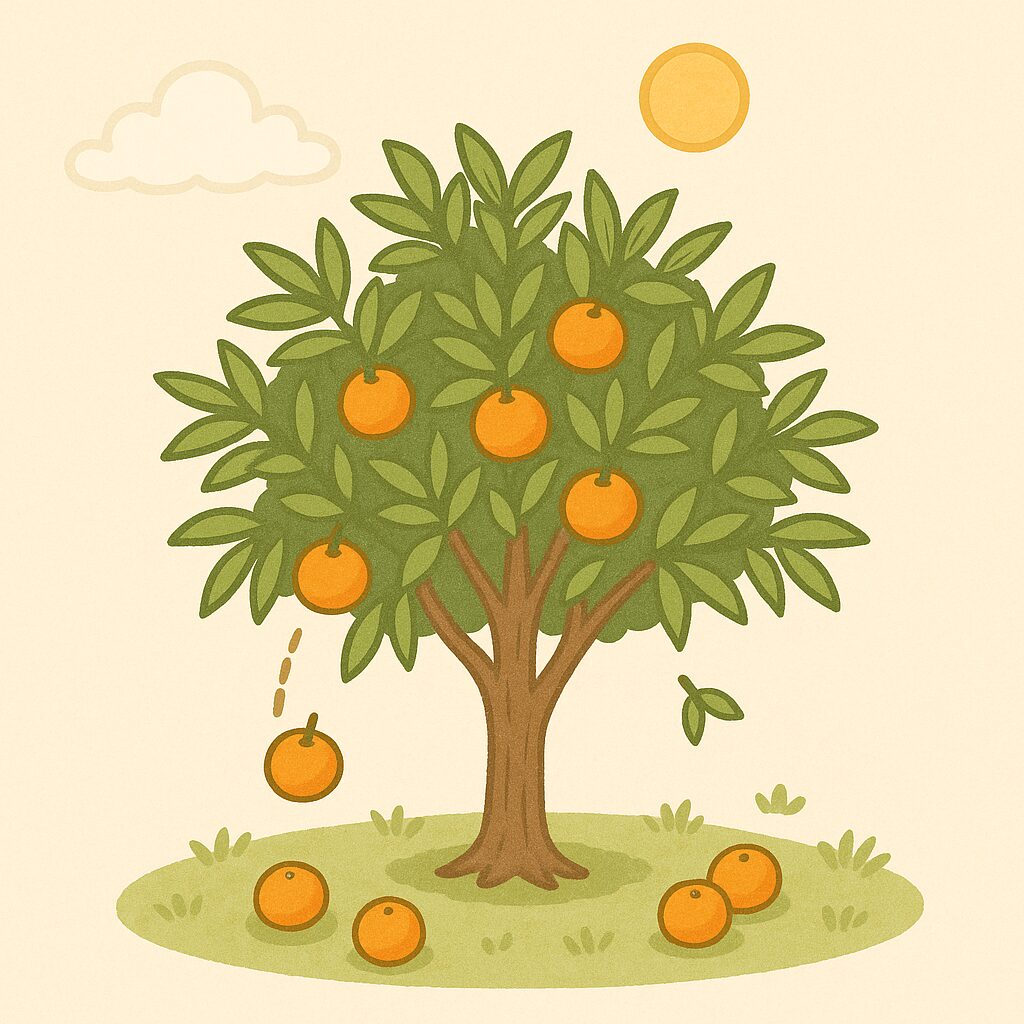
花は咲いたのに、小さな実がポロポロと落ちてしまうことがあります。これは「生理落果」と呼ばれる、みかんの木が自ら実の数を調整するために行う自然な現象であることが多いです。
生理落果は、主に6月頃に見られるため「ジューン・ドロップ」とも呼ばれます。木が自分の体力で育てられる以上の数の実がつくと、養分が分散してしまい、一つ一つの実が大きくなれません。そこで、木は自ら余分な実を落として、残した実に栄養を集中させようとします。したがって、ある程度の落果は、むしろ健全な成長のために必要な過程とも言えます。
ただし、落果があまりにも激しい場合は、他の原因も考えられます。例えば、日照不足や極端な水不足、肥料のバランスの乱れなどによって木の体力が落ちていると、必要以上に実を落としてしまうことがあります。また、カイガラムシなどの病害虫の被害によって木が弱っている場合も、落果を助長する要因となります。
みかんの木に実がなるまで何年かかる?
みかんの木を植えても、すぐに実がなるわけではありません。実がつき始めるまでの年数は、苗木の状態や品種によって異なりますが、一般的には植え付けから3年~5年ほどかかります。
市販されているみかんの苗木は、カラタチなどの台木に、温州みかんなどの品種を接ぎ木したものです。接ぎ木苗は、種から育てる「実生(みしょう)」に比べて早く実がつくという大きなメリットがあります。もし種から育てた場合は、実がなるまでには7年以上、時には10年以上かかることも珍しくありません。
最初の数年間は、木が実をつけることよりも、根や幹、枝を成長させることにエネルギーを集中させる時期です。この時期に無理に実をつけさせると、木の成長が妨げられ、その後の収穫量にも悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、最初の1~2年は、花が咲いても蕾のうちに摘み取ってしまい、木の成長を優先させることが推奨されます。
みかんの木の寿命と収穫量のピーク

みかんの木は長寿な果樹の一つですが、経済的な収穫が見込める期間には限りがあります。一般的に、みかんの木の寿命は30年~40年ほどとされています。もちろん、適切な管理を行えばそれ以上に長く生き続けることも可能です。
収穫量については、植え付けから数年で実がなり始め、木の成長とともに徐々に増えていきます。そして、植え付けから20年~30年程度で収穫量のピークを迎えます。この時期が、木として最も生産性が高い状態です。
ピークを過ぎると、木の勢いは徐々に衰え始め、収穫量も少しずつ減少していきます。また、古い木になると、病気にかかりやすくなったり、木の内部が空洞化したりすることもあります。家庭で楽しむ分には問題ないことが多いですが、収穫量を維持するためには、適切な時期に新しい木に植え替えることも視野に入れる必要があります。
庭に植えてはいけないという俗説は本当?
「みかんなど実のなる木を庭に植えてはいけない」という話を聞いたことがあるかもしれません。これは、実が「落ちる」ことから、家の運気や評価が「落ちる」ことを連想させるという、一種の縁起担ぎや俗説から来ているようです。
しかし、これはあくまで俗説であり、科学的な根拠は全くありません。むしろ、風水の世界では、オレンジ色や黄色の丸い実は金運を呼び込むとされ、縁起の良いものとして扱われることさえあります。また、お正月の鏡餅にみかん(橙)が飾られるのは、「代々(だいだい)家が栄えるように」という子孫繁栄の願いが込められているためです。
ただ、現実的な注意点はいくつか存在します。品種によっては枝に鋭いトゲがあるため、小さなお子さんやペットがいるご家庭では注意が必要です。また、アゲハチョウの幼虫やカイガラムシなどの害虫がつきやすいこと、成長すると想像以上に大きくなるため、植える場所を慎重に選ぶ必要があることなどは、植える前に理解しておくべきでしょう。これらの実用的な問題をクリアできれば、庭に植えることに何の問題もありません。
みかんの木に実がならない時の解決策
-
毎年みかんの実をつけるには摘果が重要
-
花芽を落とさない剪定のコツ
-
適切な肥料の与え方とタイミング
-
花が咲いたら行うべき手入れとは
-
みかんの木に実がならない悩みを解決
毎年みかんの実をつけるには摘果が重要

みかんの木には、実がたくさんなる「表年(おもてどし)」と、ほとんどならない「裏年(うらどし)」を繰り返す「隔年結果(かくねんけっか)」という性質があります。これは、表年に実をつけすぎて木の養分を使い果たしてしまい、翌年は花芽をつける体力が残らなくなるために起こる現象です。
この隔年結果を防ぎ、毎年安定して収穫を得るために不可欠な作業が「摘果(てきか)」です。摘果とは、つきすぎた若い実を意図的に間引く作業を指します。
摘果の目的と方法
摘果の目的は、残した実に栄養を集中させて大きく甘い果実に育てること、そして木への負担を軽くして翌年のための体力を温存させることです。
時期は、生理落果が終わった後の7月上旬から8月中旬頃が適期です。目安として、葉25枚~30枚あたり果実が1個になるように、小さい実や形が悪い実、傷のある実などを優先的にハサミで取り除きます。これにより、養分の無駄遣いを防ぎ、木全体のバランスを整えることができます。少しもったいないように感じるかもしれませんが、この一手間が翌年以降の安定した収穫につながる大切な作業です。
花芽を落とさない剪定のコツ
剪定は、みかんの木を健康に保ち、美味しい実をならせるために欠かせない作業ですが、やり方を間違えると花芽を切り落としてしまい、収穫ゼロという結果を招きかねません。
剪定の時期
最も重要なのは剪定の時期です。最適な時期は、木の活動が比較的緩やかで、花芽が動き出す前の2月下旬から3月上旬です。この時期を過ぎて新芽が伸び始めてから剪定すると、花芽ごと枝を切り落としてしまうリスクが高くなります。
剪定の基本
剪定の基本は「間引き剪定」です。内側に向かって伸びている枝(内向枝)、他の枝と交差している枝(交差枝)、真下に垂れ下がっている枝(下垂枝)など、日当たりや風通しを悪くする不要な枝を付け根から切り取ります。
特に、上に向かって勢いよく伸びる「徒長枝(とちょうし)」は、花がつきにくく、他の枝への日当たりを妨げるため、優先的に剪定の対象となります。木全体に光がまんべんなく当たるように、枝が混み合っている部分を透かすようなイメージで作業を進めるのがコツです。枝を短く切り詰める「切り戻し剪定」は、花芽を落とす可能性が高いため、初心者のうちは控えめにするのが無難でしょう。
適切な肥料の与え方とタイミング
みかんの木が元気に育ち、美味しい実をつけるためには、人間が食事をとるのと同じように、適切な時期に適切な栄養素を補給してあげる必要があります。肥料を与えるタイミングは、主に年に3回あります。
肥料は、木の幹の真下ではなく、枝の先端の真下あたりに円を描くように溝を掘って与えると、栄養を吸収する細い根に効率よく届きます。
花が咲いたら行うべき手入れとは

みかんの木に無事花が咲いたら、美味しい実の収穫に向けてあと一歩です。この段階でも、いくつか行っておきたい手入れがあります。
まず、まだ若い木(植え付け後1~3年程度)の場合は、木の成長を最優先にするため、咲いた花を摘み取ってしまう「摘花(てきか)」や、蕾のうちに取る「摘蕾(てきらい)」を行うのがおすすめです。開花や結実は木にとって大きなエネルギーを消費する活動なので、若い木に負担をかけすぎないようにするためです。
ある程度成長した木で、明らかに花の数が多すぎると感じられる場合も、摘花は有効です。特に隔年結果の傾向が強い木では、表年に花を適度に間引くことで、木への負担を減らし、翌年の花つきを良くする効果が期待できます。
また、ほとんどの温州みかんは自分の花粉で受粉できるため人工授粉の必要はありませんが、他の柑橘類を育てている場合や、虫が少ない環境では、人工授粉をしてあげると実つきが良くなることがあります。筆などで花の中心を優しくなでて、花粉をめしべにつけてあげましょう。
みかんの木に実がならない悩みを解決
この記事では、みかんの木に実がならない原因と、その解決策について詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめます。
-
実がならない原因は一つではなく複合的なことが多い
-
みかんは日当たりと風通しの良い場所を好む
-
花が咲かない主な原因は日照不足や肥料のバランス
-
窒素肥料の与えすぎは葉ばかり茂る原因になる
-
剪定の時期は花芽が動く前の2月~3月が最適
-
花芽を落とさないよう強い剪定は避ける
-
接ぎ木苗の場合、実がなるまで3~5年が目安
-
若い木は実よりも木の成長を優先させる
-
6月頃の生理落果はある程度は自然な現象
-
激しい落果は木の衰弱が原因の可能性がある
-
隔年結果を防ぐには7月頃の摘果が不可欠
-
葉25~30枚に実1個が摘果の目安
-
肥料は春・夏・秋の年3回、目的に合わせて与える
-
木の寿命や収穫ピークを理解しておくことも大切
-
「庭に植えてはいけない」は俗説だが実用的な注意点はある